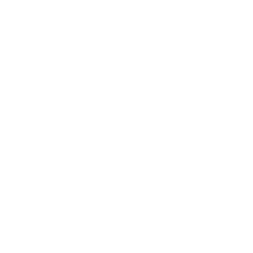砂漠の街メルズーガを出て、ワルザザードに着く頃にはもうすでに夜。
ホテルで食事。
そろそろ、スープ+前菜+タジン+パン のループに飽きてくる。
あらためて、日本にはいろんな料理があるなぁと思う。
麺もごはんもパンも、中華もイタリアンもフレンチも和食もアメリカンも。
モロッコの料理はおいしい、けれど、ラーメンとカレーライスが食べたい。
同行している松澤さんは天丼が食べたいと言っていた。それもいい。
かろうじて持ってきた梅干しとほうじ茶で日本を想う。

久しぶりのビール。乾杯。
モロッコはイスラム教の国。
基本、豚肉とお酒は口にしないという。
だから、どこでもアルコールが売っている訳ではない。
郷に入れば郷に従え、かな、と思ってきたけれど、やっぱり飲みたくなる。
だいぶこっちの時間に慣れてきたけど、疲労と眠気との闘いは続いている。
それでも、一秒一秒が貴重に思える。
感じる、見逃さない、と、脳だけは意識的に働いている。

ホテルの部屋は水道管の不具合で便座の下の床に水たまりができていた。
気づかずに踏んでズボンの裾が濡れた。
まさか!私!粗相をしたか!と思って確認したけれど、違った。水道管のもれだった。
ややテンションが下がったけど、あったタオルをバサバサと置いて、もう疲れていたから気にしないで寝てやった。よくある、よくある、気にしない。
前の日、砂漠ではwifiが繋がらずブログの更新ができていなかったので、朝出発前にアップしようということになった。そして、そのアップ作業のために出発を送らせる、ということになった。
wifiのつながる場所で、朝の時間にアップしておかないともう夜まで一切作業ができない。
基本、テキストがあがらないと写真をセレクトできない。
だから、私が遅れると全部が遅れる。
書かなきゃ、書かなきゃ、と自分を焦らせて、朝5時から7時の2時間で文字を打つ。
誤字脱字が多いのは、日本へ帰ってから修正しよう、と最初から思っている。
そして、朝。

内容が多すぎて、疲れすぎて、テキストを仕上げるのが遅れた。
ギリギリだー!!
と思って、急いでパソコンもって集合場所のロビーに行ったら、私より準備のできていないトオルさんがのんびりとした感じでソファにあぐらをかいて座っていた。
遅くなりましたー!と小走りで行ったら、
「いえ、もう今日は大丈夫です、もう無理なんで」
と、何かを悟ったような遠い目をして言われる。
そうか、無理なのか。
そうだ、無理なこともある。
無理だって言ってるんだから、無理なんだろう。
無理しちゃいけない。
無理は身体によくない。
今、無理したってろくなことない。
でも、何が無理なんだろうか・・・。
教えて欲しい。
「いやぁ・・・閉じ込められて・・・」と。
つまるところ、朝方トイレに入ってドアを締めたら鍵がかかり、その鍵が開かなくなり、何をしてもどうしても開かなくなり、叫んでも誰も来ず、あがいたりじっとしていたり、トイレットペーパーのホルダーを駆使してねじを取ろうとしたり、諦めて瞑想したり、かれこれ4時間くらい恐怖と闘っていたらしい。

早朝ミーティングに姿を見せないトオルさんを心配して、スタッフのアヤちゃんが様子を伺いに行き無事救出、となったらしい。
ということで、なにひとつ早朝に仕事ができなかったという。
このブログも、タイトルが「イマシン村」となっているけれど、なかなかその本題にいけない。
自分の、床に水たまりなんてかわいいもんだ。
ズボンが濡れたぐらい、なんだっていうんだ。
旅先で、トイレに入るときには携帯を携帯しましょう。
トオルさんは全体的に「天才」だと思う。
そういうものを引き寄せてる感じも「天才」だとしみじみ思う。
全力でテンション低いトオルさん、今日も一日頑張りましょう!
ということで、ワルザザードから約3時間かけて、イマシンという名前の村へ。

村へ行く途中には段々畑。サフランを栽培していると教えてくれた。
相も変わらず広大な景色が広がる。
イマシン村は、GOSHIMA絨毯発祥の地だという。全てはこの村から始まった。
2015年の春に発行された「GOSHIMA絨毯」を紹介する小冊子に掲載されている「モロッコ絨毯紀行」にその全てが記録されている。




イマシン村では草木で染色した糸で村の女性が絨毯を織っている。
その鮮やかな色みが村の風景と重なり合うと、強烈な力強さをもって目の前に現れる。




セカンドクオリティのデザインの一部をこの村の織り子さんが織ってくれていた。
進捗状況を工房の人たちと三方舎さんと確認する。
図案と見比べて、うまくいっているかどうか。色はどうか。みんなで確認。
うーん・・・
私たちのイメージと、織り途中のものに、少々のずれがあった。
そのズレがなんなのか。
ズレだと感じるところは一体なんなのか。
そもそもズレなのか。

現場で頭をぐるぐるさせながら考える。
染めも織りも技術はなくはない。
問題は「色」と「表現」。
どっちも難しい。
ヒシャムさんに通訳をお願いして、工房の人と色や表現の方法について調整をしていく。




ここでの制作には、ラバトにあったようなデザインペーパーがない。
紙ではなく、工房の人が織り子さんにデザイン図案の内容を口頭で伝えていく。
都市は紙で、村は人で、それぞれデザインの意図や最終型のイメージを伝える。
伝えてくれる人も、とても重要な役割を担っているひとたち。
工房にある糸の基本色は「赤、黄、緑、白、黒、青、茶」
これらの原色を基本として、多少の濃淡の幅はある。
しかし、自分が想像している以上に使える色の数が限られていた。


デザインを出したときにはある程度似通う色がある、という認識でいたが、実際に現場にくるとそうではない。こちらが出したデザインの色と工房にある染めた糸の色と照らし合わせていく。
デザイン図案を見ながら、
「これは何色ですか?」
と聞かれるけれど、だいたい微妙な混色だったりして、はっきりした名前がない。
黄色に黄土色が少し混じったざらついた茶色
青にグレーが入ったくすんだ青緑
深い橙色と真っ赤が解け合ったような暗めの赤
黒みがかった青色に少し深緑が混じった青
全てが曖昧で、微妙な色。
でも、それがすごく素敵だと思ってデザインを作っている。
しかし、糸は絵の具じゃない。
絨毯は、平面のように見えて立体物だ。
単純に、織る、という作業的な技術に加え、表現するという技術がいる。
いくらデザインがあるとはいえ、手からそのひとそれぞれの感性は表出してくる。
手作業で作られるものの大事な部分。
だから、その表現をするときに、イメージの世界を広げてくれる「色数」は重要になってくる。
色の話のなかで、私たちが「深緑」だと思っているものを「これはグレー?」と聞かれたり、「ちょっと落ち着いた白」という指示に「ベージュ」を提案されたりする場面に出くわし、これはもしかしたら、見えている色が違うのか?とも思った。
生活や経験、大地の光、日常の風景、それぞれに違う認識が生まれていくのかもしれない。
これはわからないけれど、なんだかそんなこともあるんじゃないかと思った。
工房の風景に視線と心と感覚を戻す。
染められた糸の集合体はとてもきれいに見える。
こころがわぁ〜っとなる。



きっと素材はいいはずだ。
けれど、素材がよくても、それが活きなければ、そして発展がしなければ、意味がない。
ゆっくり考えている時間など私たちにはない。
ものすごいスピードで頭を回転させ、ここの村で展開するものごとを「デザイン」からではなく「糸の色」から始めてみようということになり、どうしても色がないと成立しないデザインは保留とし、再度、色を中心にあてこんで出す、ということにした。



納期とクオリティと現地のちからとデザインがせめぎあう。
学んだのは「ゆずらない」ということ。
それは、こちらのデザインを忠実にやってくれ、ということや、無理をするということや、説得するというのではなく、私たちがこのような絨毯をつくったらすごくいいと思う!というものと、現地の感覚をすりあわせていくこと。今はまだ見えてこないけれど、今より素敵なものができるのならば、それを目指してやってみませんか。と言うためのアイディアを提示すること。こういうものが素敵だ!というイメージを具体的にもって丁寧に伝えようとする努力をすること。
嬉しいことがある。
それは、GOSHIMA絨毯を作る人々に共通していえることは、「よくしよう」という気持ちがあること。
今よりも「よくしよう」。
もっといいものを作るために「よくしよう」。
「よくしよう」という気持ちがあると、必然的によくなっていくんだと思う。
当たり前のことだけど、意識しないとよくならない。
現場に「よくしよう空気」を吹き込むことも仕事のひとつであるということも学んだ。





あらためて、
私たちはものを仕入れにきているのではない。
ものを作りに来ているのだ、ということを細胞で感じる。
現場を目撃し、現実を把握し、ひとと握手をし、対話を重ね、それぞれの思いを融合させて、今以上に誇り高い質のいいものを作りにきているのだと。
モロッコの作り手、日本のデザイナー、デザインを翻訳してくれるひと、材料を作る人、調整をする人、プロジェクトを動かす人、みんなみんなひとつのチームの一員なんだと感じる。



お昼ご飯に出してくれたタジン鍋に入っていたオリーブは綺麗に種が抜いてあって、モロッコで食べたタジン鍋のなかで、初めてオリーブの種が抜いてあるものだった。食べやすくてなんだか嬉しい気持ちになった。たいしたことじゃないんだけど、そういうささいなことが深く印象に残ることがある。丁寧でひとを想うことが出来る人が作ったんだと思う。
何度も来ている、今井さんもトオルさんも、「やっぱイマシンいいよなー」「いいですよねー」と言っていた。



きっとここはいい場所なんだと思った。
photo:Tooru Takahashi
Text:Akane Kobayashi