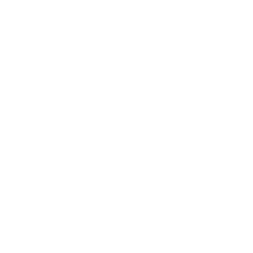夕方アイトベンハッドゥを出てマラケシュへ向かう。
ちょっと次の目的地までいこうとすると、かるく4、5時間かかる。
アイトベンハッドゥからマラケシュまでは、通常は3時間程らしいが、途中の道が雪のため閉鎖されたとのことで、回り道で約8時間。


マラケシュのホテルに着いたときにはすでに22時ころ。
もう、ほんとうに、朝から夜まで、運転お疲れさまです。
この移動時間とこれほどの移動距離を伴う旅はなかなか体験できることじゃない。
お金も時間もかけてモロッコに滞在したこの経験は、相当価値のある財産。
ここで、満を持してカップラーメンの登場。
期待していたほど美味しくなかった。
すぐに朝がきた。
朝食のとき、インスタントのみそ汁をもらった。
お湯のポットと間違えてミントティーの入ったポットから注いでしまった。
モロッコかぶれしたスカスカしたみそ汁ができた。

午前中、マラケシュのスーク(市場)へ。
モロッコの中で、一番観光客が多く訪れる場所だという。
確かに、色んな店があって活気があってふらふら歩いて見ているだけで楽しい。



このスークの中にある三方舎さん馴染みの一件の絨毯屋さんへ。
この絨毯屋のオーナーは、今井さんがモロッコで絨毯づくりを始めるきっかけとなった人だと聞いた。
三方舎さんの買い付けを見学。
ベニオワレンという絨毯を中心に、たくさんの絨毯が広げられていく。


気にいらないものは「ノッ」。
気になったものは「キープ」。
広げて見たい時は「イフタ」。
いくらか聞きたい時は「ビシャハール」。
直感で決めていくその感じは、市場のせりのようで面白い風景だった。 自分が好きかどうか、よりも、売れるか売れないか。 気に入ってくれるお客様が想像出来るかできないか。 それでも、自分の感性の琴線に触れるものに出会うことが一番の面白さかもしれない。
部屋の壁つたいにたくさんたくさん積み重ねられていて、全部を見てみたくなる。
今井さんに、これまでどうやって買い付けをしてきたのか色々聞いた。 それはそれはたくさんの絨毯を見てきた、という。 なんでもそうだけど、とにかくものをたくさん見ることは目を鍛える。 たくさん見て知る中で、自分は何がどう好きなのか、客観的に知ることができたとき、それはひとつ質の高い仕事につながるのかもしれない。
三方舎さんが選定を終えて、自分たちも、いいなーと思った絨毯を広げて見させてもらった。


今井さんが「ここまでくると、積み重ねられている状態で、端とか裏地の一部を見ればどんな絨毯か想像できる」と言う。
そんなことができるのかー、と思って、ひそかに積み重なっている中から選んでみた。
裏地しかみえなかった細かい花の柄。薄くて固めの絨毯。多分好きなもののような気がする。
と思っていたら、出してもらってみたら?と。
絶対に買えないし、買わないから、山を崩してまで見せてもらうのは気がひけたけど、気がついたら出して広げてくれていた。
素敵な絨毯だった。

ペルシャ絨毯のカシャーンシルク、だという。
カシャーンは地方の名前。
日本でシルクはいいものであるという認識が強いが、ペルシャではシルクよりもウールのほうが上質であるという。もちろん、どちらも本来の質の良さがあってのこと。
自分が知っている見たことがあるペルシャ絨毯とは違った。
きっといろんな種類があって、ひとつの方向でしかない見え方やイメージで決めつけてしまってはいけない、ものごとをもっと知ろうとしよう。
そういうきっかけを得る、こんな風に出会っていく時間と経験に、大きな価値と意味を感じる。
モロッコの絨毯にはこのような細かさはないと聞いた。ざっくりとした素朴な感じと素直さとあたたかさが魅力なのかもしれない。その反対に、ペルシャ絨毯は、曼荼羅のような、修行のような、緻密に織り上げていく忍耐力のような、怨念のような、そういう重みを感じる。
どちらもいい。
しかし、どちらかというとストイックなまでの緻密なデザインに心惹かれる。
では、どうしてこれが好きなのか。デザインが緻密だということだけではない。織り込まれている草花の絵柄は、実在するものかどうかわからないような図案。その想像力と具現化のセンス、色や、線の使い方、色のすれた感じ、とても綺麗だった。
いつかもう一度この絨毯に会いたいと思ったし、イランへも行ってみたくなった。
興味は芋づる式に繋がっていく。モロッコに来なければ出会えなかった美しいものと、他国への興味。
モロッコで、あの綺麗な絨毯に会えてよかった。
あの綺麗な絨毯が、この世界のどこかにあるんだという喜びと心のあたたかさ。
今は自分の手に入らなかったけれど、いつか、あの絨毯を買いにこれるようになって来たい、という励み。
私たち自身も、春に開設するECサイトも、このひとたちに、このサイトに出会えてよかったと思われるような、そんな存在でありたいと思う。

もうすぐ旅も終わり。
日本へ帰ってからどう動くか、限りある時間のなかで、無限の構想を作り始めている。
Photo : Tooru Takahashi
text : Akane Kobayashi